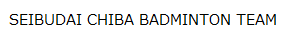知って、わかって、できるまで
【長く湿った季節】というイメージは今の梅雨には合わない気がする。雨が降るたびに、そしてニュースで『線状降水帯』という言葉を耳にするたびに、最悪のシナリオまで想像してしまうくらい今の梅雨は怖い。
その梅雨が終わろうとしている。
体育館の暑さも昔と違って過酷さを増している。聴くと隣町の中学校の体育館にはエアコンが完備しているという。当方の体育館といえば・・・、テーブルの上の温度計が悲鳴を上げている。それでも高校生たちは動き回る、跳ぶ、そして羽を追い続けている。「何かに取り憑かれているように」という表現がドンピシャである。
さて、昨今は小学生の頃からラケットを握っている選手が少なくない。だがその成長の軌跡は定規で線を引くように右肩上がりとはいかない。むしろ乱高下し、さらにスイッチバックするようにほんのわずかしか上がらず、それでも必死に上を目指そうとする選手ばかりである。
成長のトラップになる大きな要因の一つがラケットの使い方だ。その自由な使い回しができない選手が多く、この難問に向き合う選手は数え切れないほど多い。これは今始まったことではない、バドミントン競技の永遠の課題とも言えるのではないだろうか。子どもの頃からやっている今の選手はきっと上手にラケットを使い回すのではないかと思うが、ところが逆に子どもの頃握った「唯一の握り」ですべてをこなそうという選手が多い、つまりその握りで成功体験を収めている選手の動作記憶は自動化され深く根付いているのだ。残念なのは、そこに子どもの巧みさの『臨界期』だの成長のピークだのと言葉遊びや机上の空論で選手の問題解決から目をそらす指導者も多いことだ。
高校生になったって、あるいは理屈がわかる高校生だから、ラケットのハンドルの角やエンド部分の太さ、自由に使っていいことなどを「知り」、指や手のひらの添え方、力加減、肘から先の動きなどをていねいに根気強く説明すれば「わかって」くる。次はそれを「できる」段階まで、工夫を凝らした練習を繰り返す。この「知る」「わかる」「できる」を成長のチェックポイントにすれば時間はかかるが習得は可能だと実感している。
何にも言わなくても見よう見まねでできてしまう選手もいる。が、大半はそうはいかない。技芸を習得するには正しい知識と選手自身の納得が必要不可欠だ。そして繰り返す執着心、それに寄り添う協力者が選手という「人」を変えていく。前述の「何かに取り憑かれたよう」な選手は最終段階である正しい技術の技能化に進もうとしている。しかし、ここからが大変なのだ。人は機械ではない。だからその日、その瞬間の自分は、身体も心もあるいはそれらが混ざり合いながら常に変わっている。あの大谷選手だって毎日自身のフォームをチェックしたり、賞金王のプロゴルファーがこれでもかというほど毎日ボールを打ったり、夜遅くまでひとり残ってハサミを使って髪を切って切って切りまくる美容師、自分の腕前にいつになっても満足しない料理人のように道具を扱う人々にとっては「技能の迷宮」をさまよう日が続くのである。
かつて高校デビューの男子選手に、入部直後「バックハンドを使うときは、こんな風に親指を使うといいぞ」というと、その選手が「これっていいっすねぇ!」と喜んだ顔をしていた。そのときの笑顔は今も忘れられない。
「やってみせ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ」とは言い得て妙である。
さあ、今日も熱中症に気をつけて夢中になって羽を追おう!

今日の田んぼくん