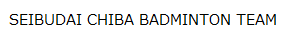自己新(ベスト)
五月晴れとはよく言ったものだ。澄み切った空に映える若緑の木々、そこに優しくゆるい風が通り抜け、信州の山々は今まさに新学期を迎えている。
ひと月早く新学期をむかえた高校生は、関東大会やインターハイに向けての大会に立て続けに挑んでいる。特に3年生にとっては正念場である。なんとか地区予選を勝ち上がり大きな大会に出場して「有終の美」を飾りたい、そう願ってラケットを握る。
しかしよくよく考えるとこれほど「アンフェアなトーナメント」はないとも思う。だって、出場する大会はどれも、選手一人一人の競技経験年数がバラバラで、それを一括して競い合わせているからだ。つまり小学1年生から経験している選手と、2年前に始めた選手が対等の土俵でぶつかり合うことになる。当然経験年数が浅い方が不利で、物の見事に場外に吹っ飛ばされる。ここ最近は中学も高校も、部活動の「学年」という壁が消えてきて、3年生をものともしない新人が次から次へと現れる。それによってチームワークの築き方も昔と違っているような気もする。
そういう我がチームにもジュニア上がり(小学生のころからバドミントンをやっている選手)、中学上がりの選手(同中学校から)に満たされ、こうした現象もしばしば起きる。
例えが極端かもしれないが、高校デビューの選手は、小学生が高校や大学の授業に放り込まれるような状態になってしまう。そしてスタートから大小さまざまなテストが繰り返され、不様な点数をとりながらも懸命に一日一日を生き抜く。ただでさえ異様な(?)雰囲気のチームに入ってしまった挙げ句、こうした真っ新なビギナーは右往左往しながら肉体的にも精神的にも大きなダメージを受け続ける。途中でリタイヤするのはさらにつらい経験になってしまうので、入部に際してはかなり念押しを繰り返し、門戸を狭くしている。
そんな中、西武台にもポツリポツリではあるが、「高校デビュー」の選手がいたし、今もいる。今年3年目を迎えたそのビギナー選手はソフトテニス部の選手だった。父親の影響だそうだが、そのことについて彼女は「子どものころお父さんがバドミントンをやっているのを見て『かっこいい!』って思ったんです・・・」と言っていた。そしてラケットをバドミントンに変えた。実質2年の経験だが着実に成長している。
この春、迎えたラストチャンス、地区の個人戦に彼女は挑んだ。
1,2回戦はまずまずのスタート、その日のメインイベント、県大会をかけた3回戦の相手は、元気のいい、息の合ったペアだった。その選手(ここからはミカちゃんにしよう)は、ひとつ後輩と組んでいる。後輩は小学生からやっている選手だが、先輩にとって大切な一戦、と思うと硬くなりミスも増えていった。他方ミカちゃんは表情もよく果敢に後方から攻撃し、ディフェンスも固く、そして時に上手に逃げ、今までで最高のプレーを続けた。結果は残念ながら敗れたものの「ベストパフォーマンス(陸上などでいえば『自己ベスト』)」で幕を下ろした。直後はまだ汗も引かず、紅潮した表情で眼も生きいきしていた。こちらも少しホッとした。
しかし夕刻、大会も終盤の会場では、西武台同士が、そして他校もそれぞれ白熱した試合を繰り広げ大応援合戦で盛り上がった。その後、まるで花火大会のフィナーレを終えたのような雰囲気で体育館を出た。
エントランス前に整列する。中央後列に控えめなミカちゃんはいた。「ミカちゃん良かったよ、ベストだったね!」と話しかけながら彼女の顔を見ると、そう白、まるでプールから出てきたような色になって、泣きそうになっている・・・。
「なんでこのコートに私がいないの・・・。また私は観客席からの応援団だ・・・。」と、ついさっき包まれていたライブ感の中で、心が急降下したのかもしれない。それでも彼女は眼に力を入れて涙を止めた。それははっきりわかった。私は「泣かないで!」と内心思った。それはこちらもダメになりそうだったから。「だけど、今日はいい試合ばかりだった!」と自分に言い聞かせるようにして、あえて彼女を心に入れないように逃げ、そしてその場を去った。
「大会なんてそんなもの」「スポーツなんてそんなもの」と言われる。私はその「そんなもの」ということについて考えた。
『弱肉強食なんだ』『強いものだけが陽の目を見る、残酷なものだ!』という見方があるが、私はちがった。
彼女が真新しい制服を着て体育館に足を踏み入れた日から、遠い通学を繰り返し、できない練習の日が続いても、そして時には同級生のレギュラーとは違った会場に分けられても、そして負け続けても・・・、暑い日でも寒い日でもめげずに練習に参加して決して逃げることはなかった。
これらはどれひとつとしてウソではなく、彼女はそれこそ一球一球、そして一日一日を石に刻むような2年間を送っていた。
技術もゆっくりだが確実に成長していった。
飛ばないクリアが奥まで届くようになり、ゆるいスマッシュが、飛び跳ねながら連続で強打できるようになって、当たらなかったバックハンドは、相手からの強いスマッシュをクロス奥までリターンできるし、動きもスムーズになって、時と場合に応じたステップや身のこなしで、安定させて長続きできるようになってきた。
しかし、大会はそう甘くない。やはり【2年間は彼女にとって短すぎた(英作文の問題のようだ)】。一流になるためには「十年、一万時間が必要」などと言われるが、あと少しの経験時間が必要なのだろう。
「結果がすべてではない。そこまでの過程が大切なんだ!」という青臭いフレーズはよく耳にするし、そうだなぁとも思う。が、ついつい結果ばかりに目も心も持っていかれる。昨日の大谷選手のホームラン、大相撲の伯桜鵬の白星・・・、一喜一憂している。人情と言ってはそれまでだが。
しかし、私たちのような立場のおとなはそれではいけない。ドラマの結末ばかりではなく、ワンシーンワンシーンで見せる役者の演技を目に焼き付けて、その瞬間の微笑やこぼれ落ちる涙の訳をずっと引きずりながらラストに向かわなければならない。音楽でもスポーツでも同じだろう。ことにスポーツにおける【自己新】は大切な瞬間であり、我々は心の底から敬意を払い、そして祝福しなければならない、と考えている。スポーツとは「そんなもの」だから。
今年度から正式にマネージャー登録の選手でも試合出場が可能になった。一度ミカちゃんが団体戦のメンバーに入ったとき、「先生方が『ミカちゃんもチームのメンバー、一員なんだよ!』と言われたとき私はとてもうれしかった」と言っていたことが頭から離れない。末っ娘ばかりの同級生レギュラーの間でも陽気にふるまい、ムードメーカーにもなっている。よい友に恵まれ、こうして人生は織りなされていく。スポーツとは「そんなもの」だから。
彼女は大学進学を目指している。今は彼女に勝っている選手も、数年後は敵わぬ選手になっていることだろう。そしてその時にこの貴重な高校生時代に思いをはせてほしい。
高校生の指導者は、目の前の高校生とともに歩むために常に「青臭い」話を聞かせなければならない。そしてそれを、し続けなければならない。全身青汁になるまで。

お父さん、娘さん頑張ってますよ!