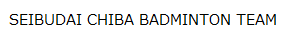銀傘 たった一回の負け
梅雨の狭間。広がる田の穂がそろそろ出てくる頃、蛙の鳴き声にも張りが出てきている。今日も暑くなりそうだ。
インターハイ予選を中心にした一連の大会シーズンが終わり、期末考査を挟んで次の追い込みシーズンを迎える。3年生の中にはもうすでに受験勉強にシフトし、文字通り猛勉強に励んでいる者もいる。当の本人は「疾風怒濤」の真っ只中だろうが、バドミントンでも勉強でも一途に打ち込む姿はまぶしいくらい輝いて見える。
高校スポーツ、いやジュニア期のスポーツ界に今変革が訪れている。いわゆる「全中」の種目削減、全国大会などの日程縮小、団体戦(学校対抗戦)の存続・・・、噂と憶測が低空飛行をしながら乱気流に巻き込まれている。
高校スポーツの源流で聖地になっているのが、高校野球で甲子園だろう。灼熱の太陽をあの銀傘が跳ね返し、場内は異様とも言えるほどの熱気と感動につつまれる。作家阿久悠は 『甲子園の詩』の中で、「敗れざる君たちへ」と題し、一握りの栄光の影に隠れている無数の青春群像をていねいに描いている。当たり前だが優勝した選手以外はたった一回の「負け」を等しく体験しながら青春の1ページを閉じる。つまり地区予選でも県大会でも、関東やインターハイでも「たった一回の負け」をほとんどの若者が味わい経験するのだ。そこから新たな人生のステージに立つことになる。むしろ時間的にはその後のステージでの出番の方がはるかに長い。こうした若者の内面まで深く切り込み、それを伝え、育む文化が「高校野球」にはあり、甲子園に行けばそれをいつでもなんとなく感じることができる。ちなみに高校野球はいわゆる高体連とは別の組織で独立した運営を行っている。バドミントン競技はそのほかの競技と同様、高体連の傘下のもと大会が行われている。もちろん高野連でも高体連でも様々な問題や課題を抱えながらも前向きに粛々とその役目を果たしているのだろうが、文化としての高校スポーツの色合いには大きな差がある。
私が中学3年生の夏、受験勉強がてら朝日新聞の「天声人語」を毎日スクラップしていたら、「背番号15は泣いている」というフレーズで始まる甲子園モノがあった。現物もなく記憶だけが頼りだが、ベンチに入れる選手には限りがあり、ある番号からはベンチ入りができない。その背番号を手渡された選手は(もちろんそれ以降の選手は全員ベンチには入れないのだが)悔しくて宿舎でみんなが寝静まったころ、ひとり枕を涙で濡らす・・・、たしかこんな話だったと思う(その昔は14人まで、そして18人に、今は20人までベンチに入れるそうだ)。これは、「たかがベンチだろう、甲子園に行けたのだからいいではないか」などと軽くあしらえない話なのだ。これこそ「たった一回の負け」から学ぶ大切な場であり、高校生に携わるものたちのこだわりでもある。インターハイ予選での団体戦で「ベンチ」が置かれていなかった。いろいろ厄介な問題があったのだろうが、まさにこの「差」を感じた。さらに応援をさえぎり、会場をコントロールしまくる放送・・・。残念で情けなかった。
「そんなこだわりなんて今の高校生にはありませんよ。負けたってケロッとしてますよ。」などと私に話す方もいる。たしかにケロッとしている選手もいることはわかる。だけど本当に「ケロッと」しているのだろうか。私はこの「たった一回の負け」を大切にすべきだと思っている。それはそこから無限の可能性への旅が始まるからだ。だから私たちはその「負け」を大いに演出すべきだとも思う。甲子園の選手が砂を持ち帰るように。
この経験を陰ながら支えやさしく励ましているのが親や家族、そして仲間たちだ。ことに仲間は、互いにその「たった一回の負け」を見届け合う。そんな儀式でもあるから、それから長く杯を交わすたびにその話題になるのは当然だろう。そしてその大切な思いを次の世代に伝える。これを「教育」と言ってもいい。
三位決定戦で破れたモノは「二回の負け」を、そしてもしリーグ戦なら、もしダブルスとシングルスを兼ねていたら・・・、もう何回でもいい。何かが学べるはずだから。
あと少しで梅雨が明ける。甲子園の銀傘が跳ね返す太陽は佐賀の空にも輝く!
古い曲だが、こんな時思い出す歌詞だ。

出穂間近!