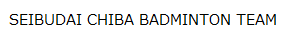四十年一昔
好天の山々、木々は少しずつ色合いを増しながら冬支度を始めた。ということは新人大会も近い。
最近、テレビやネットのスポーツ情報で日本のバドミントン選手の活躍を耳にしない日はないくらいだ。先日、ある方から「日本のバドミントン、今すごいですね」と、その後に「だって、外国人選手がいないJAPANですよね・・・」と言われた。それもそうだな、外国人選手がJAPANとして活躍している競技は珍しくない。私はその善し悪しではなく、その意味を考えた。
40年以上前の1960年代、世界バドミントン界のトップの座にいた日本はその後1980年代から30年以上低迷期を続けてきた。日本が勝てないだけでなく、お家芸のインドネシアが強く、とりわけ中国選手の快進撃はすさまじかった。その合間に韓国が、デンマークが・・・と我が国の入る隙は全くなかったのだ。
私がチームを受け持つようになったのがその頃で、日本のかつての栄光はどこに行ってしまったんだろう?何が違いなんだろう?と考え何度も中国に足を運んだのもそうした素朴な疑問を解きたかったからだ。しかし、いくら訪中してもその核の部分はなかなかわからなかった。
「そりゃ違うんだよ。だって彼ら(中国人選手)たちは生活がかかっているんだよ。部活や趣味の延長でやっている日本とは比べる尺度が違うんだ」と幾人もの方々に幾度も言われた。しかしそれだけでは、あるいはそれ自体が当を得ていない、そんな確信はあった。中国の選手、指導者のバドミントンという競技への考え方や育成のシステム、指導理論が我々のそれとは大きく違っていたからだ。だけどそれをそのまま日本に持って来てもダメなこともわかっていた。
しかし、そんなモヤモヤした月日が長く続いていた日本で、決して諦めずにひたむきに努力を続けていた指導者と選手がいた。中高生に、その多感な時期に海外の本当のレベルを自ら体感したり、跳ね飛ばされ続いても繰り返し挑戦する経験を与え続けてきた。言葉や文化が違う中、予算も限られ質素ではあるが真面目に、ヨーロッパ、アジアへと選手を連れて犠牲的精神で引率指導をなさった先生方には感服するばかりである。
その厳しくも前向きな選手の育成は規模こそ小さく即効性はなかったが、次第に協会や業界、そして手弁当で子供たちをコツコツと育て上げてきた多くの方々の間を次々に共鳴し選手の琴線をはじく結果になった。即効性のある外国人選手で応急処置するようなことはしてこなかった。
さらに忘れてはならないのが用具の変遷である。ラケットやガットの性能が上がったということだけではなく、低迷期にほんの少しだが確実に光る希望が見え始めたとき、中学生もそれまで20年間以上使用していた合成球から現在の水鳥球を使うようになったことだ。すると小学生、中学高校、社会人と直線的な成長過程が見えてくる。だが私はそれだけではないと思う。関わる方々との交流の輪が大きく広がったことも大きいと思う。合成球だと敬遠気味だった大人たちや、高校生、大学生が中学生と打ち合うようになった。さらに部活動への外部コーチ導入制で拍車がかかり、少なからず練習や試合のレベルが向上し、小学生の頃から成長の階段を可視化できるようになって、継続的に見続けて育まれようになったのではないだろうか。
今日もフレンチオープンで日本人女子選手が単複で決勝に臨む旨のニュースを見た。この選手たちも多くの方々が夢描いた希望の階段をコツコツと上ってきた選手たちだ。
しかし、世は流れは、その変化を止めることは決してない。次の夢と希望の階段、その設計図をまた新たに描かなければならない気もする。


鬼怒川で季節外れの桜の花を観ました。