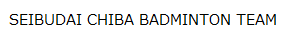コトダマ
年末、最終コーナーに突入する前に定期考査が待っている。明日が最終日だからヤマ場は越したのだろうが、苦手教科が最終日に連続することだって珍しくない。得意教科のないものにとっては毎日が苦手教科の連続だが。ガンバ!
BWFワールドツアーファイナルズ2018が中国の広州で行われていた。最終日決勝戦では日本勢が苦戦していたが、個人的には松友選手が優勝したので今年の締めくくりとしてありがたく納めさせていただいた。
最近はこうしてバドミントンをテレビで観戦できるようになり何よりであるが、いつも思うことがある。インターバルでのコーチと選手とのやりとりだ。自分自身も関わることだが、人様のそれをじっくり見るのはあまりないので興味がわいてくる。大概コーチは①熱狂的ボディーランゲージ派、と②撃鉄怒り収まらない派、そして③何言っているのかわからない「自己完結型」、さらに④このときばかりと笑わしたくてしょうがないオヤジタイプなどに分類できる。中高生の場合②の対応で何故かラリー中より緊張が高まる経験をしている場合が多いようだ。一方、トッププレーヤーたちのそれを観ていると、コーチは同じような感じだが、「この人って聞いているのかな?」と思う選手や完全無視って感じてしまう時もある。だけど通じているんだろうな、と思って観ている。
インターバルの短い時間に選手に与えるより効果的な言葉はどこかにはあるのだろうが、その場になると思いつかずアタフタしているのが現状だ。サッカーや野球、アメフトのロッカールームでの監督やコーチによるショートスピーチや、リング上の血と汗にまみれたボクサーの耳元でささやくセコンドの言葉当たりにはそれなりの『語録』があり、映画やドキュメンタリーでグッとくるシーンを観たこともある。大切な時に大切な人に大切な言葉を用意しなければダメなんだろうな。
南米のアマゾン辺りに住んでいる先住民族を「イゾラド(隔絶された人々)」とスペイン語で言うらしい。というのはそのドキュメンタリーを観たのだが、「アウラ」と「アウレ」というイゾラドの男ふたりを長期にわたって取材してきたものだ。イゾラドだから言葉がわからないんだ、彼らが口にする言葉はその近辺の部族でも住民でも学者でもわからない。「イッテQ」などでは「ダブル通訳」でやっと日本語までたどり着くのは観ていたが、今回のそれは「誰もわからない」から大変だ。スマホでググってもわからない。だからってふたりは無口というわけではない。夜になると粗末な小屋からふたりの会話がずっと続いていた。おしゃべりは好きなんだな。そこに現れた「隣に住んでいる白人」という大柄な男性には微妙にふたりの言葉がわかる。彼は言語学者で国の仕事でふたりに30年前から接していたそうだ。細かに単語をノートに記録していたが、それでもカタコト、それ以下であるようだ。ただ、そのシーンからわかったのはこの言語学者は「言葉」よりふたり(実は長い取材中に相方のアウレが亡くなってしまって、途中からアウラだけになってしまったのだが)の「心」を察し、つかんでいるような気がした。この辺りにヒントがありそうだ。
だから日本の鎖国、江戸時代に長崎で通詞をしていた人たちの苦労やたくましさは私にでも推測できる。言葉は我々人間にもたらされた第二の魂だと思っている。言葉ひとつで立ち上がれないほど傷つく場合もあるし、命が救われ、みんなの心が潤うることがある。言霊とはよく言ったものだ。
同じ日本語を母語にしている選手とだって全く通じない、こちらの気持ちが伝わらないことはしょっちゅうある。難しいが「相手の気持ち」をつかむ作業は絶対に必要だ。だが、それ以上にダブルスの場合はインターバル中のふたりの会話が最も大切だと思う。だから少しは早めに切り上げてふたりに時間をあげたいと思っている。シングルスの場合は?もちろんその選手が自分と向き合う時間を残さなければならない。しかし孤独にさせないようにニコリとするのも良いアドバイスだ。
 アマゾンって通販ではありませんよ。
アマゾンって通販ではありませんよ。