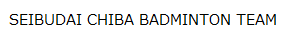麦秋
広がる田園地帯が薄黄色に輝き、先端には絵に描いたような穂が実っていた。麦にとっては今が秋、そしてアッという間に収穫された。隣の水田の稲はひざ下あたりまで育っている。
この季節は毎年、関東大会とインターハイ予選が続く。とりわけ3年生にとっては自分たちのステージを思う存分演じ、次の世代に目に見えない大切なバトンを渡すビッグイベントが続く。
おそらく西武台は30年以上同じ高さで飛んでいると思う。関東大会初出場の頃には決して上位に入ることは叶わないと思っていた。スカウトをして人工的な出会いを作り上げ、計画的にチームのピーキングを求めれば上位には・・・、と考えたことはなくはない(だから「あった」ということです)。しかし、連綿と続く巣立つ選手たちに「変わったね」と言われたくない、ただそれだけで今に至る。
それがどういうことか、いわゆる「強豪校」と言われる学校が入れ替わり立ち替わり乱高下している。したがって相対的に西武台が上位に入るチャンスが廻ってきた。
女子チームは連続30回出場で表彰を受けた。そんな年には最後の表彰式までいたいところだが、組み合わせを見た途端に「それはないな」と思っていた。周囲の不安をよそに、コートを元気いっぱい走り回る彼女らが心の中の霧を振り払った。いつもながら合い言葉は「この体育館で最後の最後までバドミントンをやろう!」だ。そのとおりやってくれた。ブラボー!つうか何しろ疲れただろう。
続くインターハイ予選でも、自己ベストを求めて健気にそして明るく羽を追っていた。こちらも最後の最後までコートに立っていた。
「学校の部活問題」ににわかにスポットライトが当たり、「西武台も厳しいですよね・・・」などとご指摘を受ける場面もないわけではない(だから「ある」ということだ)。考えなければならないこと、変化を予測してそれぞれの対応策も考えなければならない・・・、と野暮な大人が知恵をしぼってしかめっ面している。まるで麦の秋ならぬ部活動の秋「部秋」だ。それに対して彼ら、彼女らは「そうですか・・・」とは言いながらも、自分の前しか見ていない、見えない。今このときを燃え尽きるまで走り込む。
内田樹さんはこう言っている。
"日本の部活は「貧しい家の子どもたちでも自分の潜在可能性を見出す機会が与えられ、その開発を学校が支援してくれる」仕組みです。列強に伍するために近代日本には「貧しい家の子どもの能力を死蔵するままにしておく」ことができなかったからです。結果的にそれは教育的に機能した。子どもたちを競争させたり格付けしたりするための制度ではありません。子どもたちの潜在可能性を最大化するための仕組みです。教育者の仕事です。部活のせいで教員の負担が過重だというのなら教員を増員して対処すべきです。学校はこの貴重な教育機会を放棄すべきではありません。"
わたしもそう思う。彼ら、彼女らを見てみれば当然そう思う。悪い話は人の心にヘンな満足感と偏った正義感を植え付ける。悪い話ばかりじゃないのに。
さて、梅雨空明けるとすぐにインターハイだ!(今年は少し早くなっています)

関東大会(埼玉県熊谷市) おとなりの羽生市 利根川土手と鉄橋